あわせて読みたい


投稿日:2025年11月15日

不動産を売却する際、売主様にとって最も気がかりなのが「売却後のトラブル」ではないでしょうか。
特に、引き渡しを終えた後に物件の欠陥が見つかった場合、売主は買主に対して「契約不適合責任」という重い責任を負うことになります。これは、高額な修理費用や損害賠償につながる可能性があるため、絶対に避けたいリスクです。
しかし、この責任を免れるための手段として「免責特約」があります。
本コラムでは、契約不適合責任とは何か、そして売主様がリスクを回避できる免責特約のメリット・デメリットと注意点について、初心者でも分かりやすいように徹底解説します。リスクを正しく理解し、安心して取引を完了させましょう。

不動産の売買契約において、引き渡された不動産が、種類・品質・数量に関して契約で定めた内容に適合していなかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことを「契約不適合責任」といいます。
| 買主が請求できる権利 | 内容 |
|---|---|
| 履行の追完請求 | 契約に適合した状態にするよう、修理や代替品・不足分の引渡しなどを求める権利。 |
| 代金減額請求 | 契約通りにするよう要求しても売主が応じない場合などに、不適合の程度に応じて代金を減額するよう求める権利。 |
| 損害賠償請求 | 不適合によって生じた損害の賠償を求める権利。 |
| 契約の解除 | 契約の目的が達成できない場合に契約を解除する権利。 |

契約不適合責任の免責とは、売主と買主が事前に合意することで、売主が負うはずの責任を、すべて、または一部負わないことにするという取り決めです。
しかし、この免責特約が適用される条件は、以下のとおり売主が誰かによって大きく異なります。
| 特約内容 | 適用例 | |
|---|---|---|
| 全面免責のケース | 「売主は、本物件に関する契約不適合責任を一切負わないものとする。」 | 引渡しから1週間後に給湯器が故障した場合でも、買主は売主に修理費用を請求できない。 |
| 期間制限を設けたケース | 「売主が契約不適合責任を負う期間は、引渡しの日から3ヶ月間とする。」 | 引渡し後3ヶ月以内に雨漏りが発覚し、買主が通知した場合は、売主が修理費用を負担する。しかし、引渡し後3ヶ月以降に雨漏りが発覚した場合、売主は期間を過ぎているため免責され、買主が自己負担する。 |
| 特約内容 | 適用例 | |
|---|---|---|
| 期間制限を設けたケース | 「売主が契約不適合責任を負う期間は、引渡しの日から2年間とする。」 | 引渡し後2年以内にシロアリ被害が発覚した場合は、売主が修理費用を負担する。しかし、引き渡し後2年以降に発覚した場合は、売主は期間を過ぎているため免責され、買主が自己負担する。 |
| 特約内容 | 適用例 | |
|---|---|---|
| 全面免責のケース | 「売主は、本物件に関する契約不適合責任を一切負わないものとする。」 | この特約は無効となるため、売主は民法の規定に基づき損害賠償責任を負う必要がある。 |
| 期間制限を極端に短く設けたケース | 「売主が契約不適合責任を負う期間は、引渡しの日から3ヶ月間とする。」 | 消費者契約法に基づき、3ヶ月という極端な短期間は買主に不利であると判断され、無効となる可能性が高い。 |
| 免責を一部限定するケース | 「売主が契約不適合責任を負う期間は、引渡しの日から1年間とする。ただし、売主の故意または重過失による損害賠償責任については、免責されない。」 | 損害賠償責任の一部(軽過失によるものなど)を免除するに留まり、期間も合理的な範囲内と判断され有効となる可能性が高い。 |
【例】: 以前から雨漏りがあったことを知っていたのに、「免責特約」があるからと買主に告げずに売却したケース。
【例】:「引渡しから1年間の保証」と定めるべきところを、「引渡しから3ヶ月しか責任を負わない」とした特約は宅建業法に反するため無効となる。
【例】:不適合の通知を「引渡しから24時間以内に行わなければ責任を負わない」とするなど、極端に短い期間を定める特約は消費者契約法に反するため無効となる。


ここからは、実際に契約不適合責任を免責にする場合のメリット・デメリットを売主側と買主側それぞれの視点から解説していきます。
また、売主が押さえるべき注意点についても併せて紹介します。
〈売主側〉
| メリット | *引渡し後の修補や損害賠償といった金銭的・時間的な責任を負うリスクを原則的に回避できる。 *責任を負わない分、物件価格を低めに設定でき、早期の売却や買い手の確保につながりやすい。 |
|---|---|
| デメリット | *宅建業法や消費者契約法などの強行法規に違反した場合、特約自体が無効になり、全責任を負うことになる。 *買主にとってリスクが大きいため、取引が成立しにくくなる、または価格交渉で不利になることがある。 |
| メリット | *保証がない分、相場よりも安く物件を購入できる可能性が高い。 *築年数が古い、あるいは保証付きでは手が出せなかった物件を購入の選択肢に入れられる。 |
|---|---|
| デメリット | *引渡し後に欠陥が見つかった場合、その修繕費用を全て自己負担しなければならない。 *自己負担する修繕費が高額になり、トータルの支出が割高になる可能性がある。 |
①「経年劣化による設備不具合は免責」など、範囲を明確にする
免責とする範囲を「すべて」とするのではなく、具体的にどの部分、どの事象を免責とするかを明確に記載することが重要です。
② 曖昧な表現は避け、弁護士や専門家に相談して契約条件を明確化
法律の専門用語や解釈の余地がある表現を避ける必要があります。一般的な知識を持たない買主でも理解できるよう、平易かつ明確な文言を使用しましょう。不動産取引に詳しい弁護士や宅地建物取引士に契約書の内容をチェックしてもらい、免責特約が法的に有効であるか、また買主保護の観点から問題がないかを確認することが賢明です。
③ 契約書作成前に必要書類を確認し、重要事項説明で買主と共有
買主が契約内容や物件の状態を十分に理解した上で契約を結ぶことが、免責特約の有効性を裏付ける重要な要素となります。売主は、仲介業者が重要事項説明を適切に行えるよう、物件に関する情報や書類を正確に提供し、免責の内容やその影響について買主と認識を共有しなければなりません。
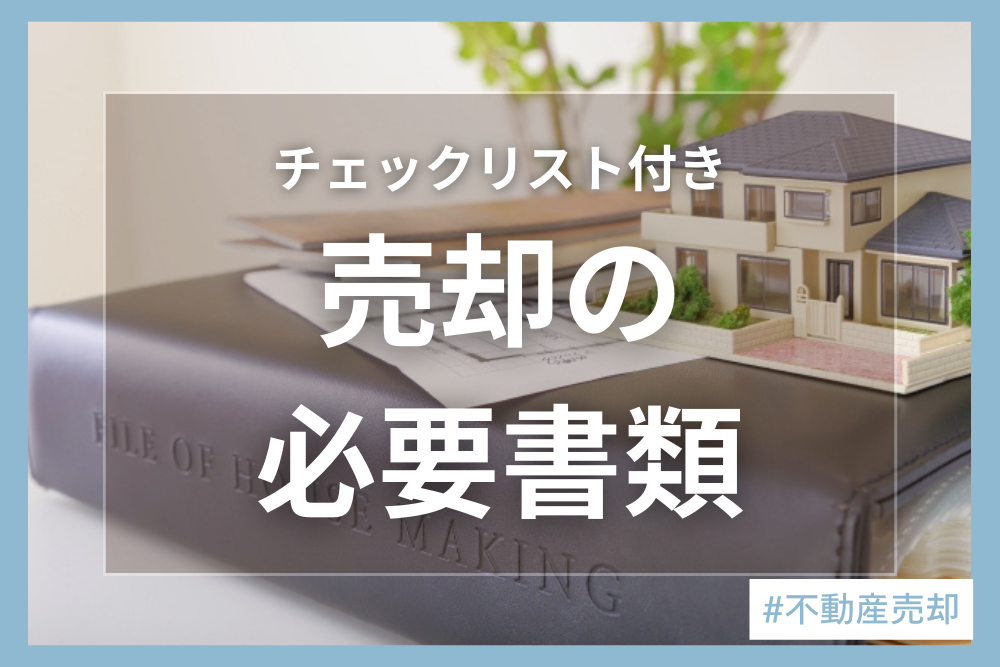
不動産売却における【契約不適合責任】と【免責特約】は、売主様が売却後の金銭的なリスクから身を守るために欠かせない知識です。
免責特約のメリット・デメリットや注意点を正しく理解し、引き渡し後の予期せぬ不具合に対する修理費用や損害賠償からご自身を守りましょう。
弊社では、お客様が安心して不動産を売却できるよう、専門的な知識をもつスタッフが安全な取引を全力でサポートしております。
不動産売却について少しでも不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
 物件を実際に探してみよう!
物件を実際に探してみよう!不動産購入の知識がついたら物件を探してみよう!会員登録すれば物件検索の幅がグッと広がります!

メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ