北側斜線制限とは?適用エリア・計算方法・緩和条件をわかりやすく解説
投稿日:2025年11月07日
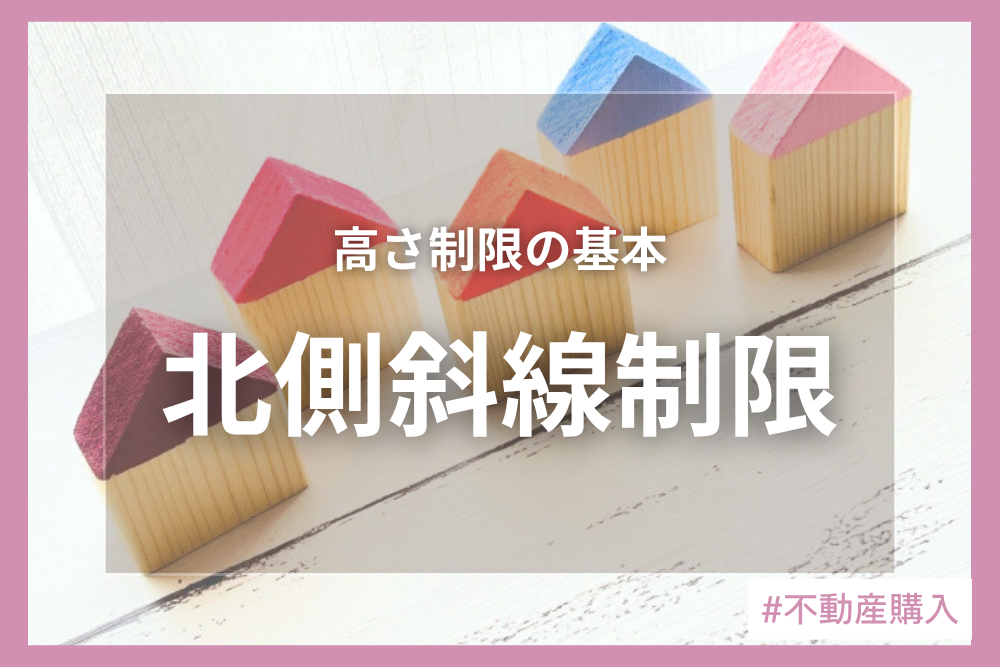
お家を建てようか検討された時に、ホームページなどで「北側斜線制限」という言葉を目にしたことはありませんか。
北側斜線制限とは、建物を建てる際に「お隣のお家の日当たりを妨げないようにする」というルールのひとつです。
しかし、このルールがあることで、日当たりや風通しが確保され、住みやすい環境、住みやすい環境が守られています。エリアによっては、北側斜線制限が適用されない場合や一定の条件を満たせば制限を緩和できるケースもあります。
今回のコラムでは、「北側斜線制限とは」という基本から、適用されるエリア、具体的な計算方法、家づくりへの影響、そして緩和条件までを説明します。最後に土地購入前に確認すべきチェック項目もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。
-
北側斜線制限とは
-
-
北側斜線制限とは、建築基準法で定められている高さ制限の一つで、北側に隣接する住宅の日当たり(採光)や風通しを確保するために設けられたルールです。
このほかにも、高さに関する制限には「道路斜線制限」や「隣地斜線制限」などがあり、建物を建てる際にはこれらを総合的に考慮する必要があります。
北側斜線制限が適用される用途地域
まず用途地域とは、暮らしやすい良好な市街地を形成するために、13種類に分けられたエリアのことです。騒音や公害を防ぎ、生活環境を整える目的で、それぞれのエリアにおいて建築できる建物の種類や高さが制限されています。
その中で、北側斜線制限が適用されるのは、以下の日照や静かな環境を重視する住宅エリアです。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
※日影規制(日影による高さの制限)が適用される場合は、北側斜線制限は適用除外となるケースもあります。
自分の土地の用途地域の調べ方
1.インターネットで検索
インターネットで「○○(市区町村) 用途地域マップ」と検索すればご自身で簡単に調べる事ができます。地図上で色分けされているため、とても分かりやすいです。
2.役所の窓口で確認
市役所の都市計画課などの窓口で閲覧することもできます。その際は、購入を検討している土地の住宅地図を持参すると場所を特定しやすくなります。
3.周辺の建物を観察する
その土地の周辺にある建物の形状を見るのも一つの方法です。上階部分が切り取った斜面のような形であったり、マンションのルーフバルコニーが階段状になっていれば、北側斜線制限がある可能性が高いと判断できます。
-
北側斜線制限で生じる3つの影響
-
-
1. 建物の高さが制限される
用途地域ごとに基準が異なり、第1・第2種低層では5m、第1・第2種中高層では10mが基準になります。
特に注意したいのが、低層住居専用地域で適用される「絶対高さ制限」です。これは北側斜線制限とは別のルールで、「建物の高さは10m(または12m)以下にする」という制限です。
北側斜線制限をクリアしていても、この絶対高さ制限を超えてしまうことはできないため、両方のルールを守る必要があります。
2. 屋根の形状が制限される
北側の高さを抑えるため、屋根の形が「北側斜線」に沿って斜めに切り取られたような形状になることが多くあります。
切妻屋根、寄棟屋根、片流れ屋根を選択するケースが多く、特に、片流れ屋根はスマートな形状であるため、近年よく見られます。敷地の状況によっては、敷地北側に十分な屋根面積を設けられないケースもありますので注意しましょう。
3. 間取りや設計の自由度が下がる
△部屋が狭くなる
北側斜線制限の影響を最も受けやすいのが、建物の北側に配置する部屋です。2階や3階の北側の部屋は、天井が屋根の形に合わせて斜めになり、居住スペースが狭く感じられることがあります。
△収納スペースが限られる
壁が斜めになることで、クローゼットや棚などの収納を計画通りに設置できない可能性があります。
△大きな窓を設置しにくい
北側の壁の高さを確保できず、採光や換気のための窓が小さくなったり、希望の位置に設置できなかったりする恐れがあります。
北側斜線制限の計算方法
低層・中高層の地域によって基準が異なります。
| 対象地域 | 起算点 | 勾配 | 計算式 |
|---|
| 低層住居系 | 5m | 1.25 | (水平距離 × 1.25) + 5m |
|---|
| 中高層住居系 | 10m | 1.25 | (水平距離 × 1.25) + 10m |
|---|
|
※水平距離とは建物の真北方向にある隣地境界線、または前面道路の反対にある境界線までの距離です。
具体的な計算例
例)第一種低層住居専用地域で、北側境界線から2m離れた位置に建物を建てる場合
①用途地域が「第一種低層住居専用地域」なので、起算点5m・勾配1.25の計算式を使います。
②計算式: (水平距離 2m × 1.25) + 5m = 7.5m
③結果:その位置で建てられる建物の高さは、7.5mまでとなります。
もし境界線から1mの位置なら (1m × 1.25) + 5m = 6.25m 、4mの位置なら (4m × 1.25) + 5m = 10m となります。このように、北側の境界線から離れる(南側へ行く)ほど、高い建物を建てることが可能になります。
北側斜線制限が緩和される条件と注意点
厳しい北側斜線制限ですが、特定の条件を満たすことで制限が緩和され、より高い建物を建てられる可能性があります。
緩和条件①:敷地の北側が道路に面している
敷地の北側が道路に面している場合(北側道路)、北側斜線の起算点は、隣地境界線ではなく「道路の反対側の境界線」から取ることができます。反対側の境界線から5mまたは10mの高さを取って斜線を引くので、大きく緩和される場合もあります。ただし、この場合は「道路斜線制限」も同時に適用されるため、北側斜線制限と道路斜線制限のうち、どちらか厳しい方の制限が適用されるので注意が必要です。
緩和条件②:隣地との高低差がある
敷地の北側にある隣地や道路が、自分の敷地よりも1m以上高い場合、高さが緩和される可能性があります。この場合の計算式は、「(高低差 − 1m)÷2」 を使用します。
例えば高低差が3mあった場合、(3m - 1m) ÷ 2 = 1m となり、起算点の高さ(5mまたは10m)が1m高い位置(6mまたは11m)からスタートできるイメージです。隣地境界線が高くなるのでその分高い建物が建てられます。
緩和条件③:天空率を適用する
北側斜線制限のルールを適用した建物よりも、これから建てようとしている建物(計画建築物)のほうが、北側の隣地から見た空の見える割合(=天空率(てんくうりつ))が同じ、もしくは上回っていれば、北側斜線制限そのものの適用が免除されます。
これにより、斜線制限のラインを一部超えていたとしても、家を建てることが可能になります。ただし、天空率の計算は非常に専門的で複雑なため、必ず設計士への相談が必要です。
【注意点】北側が「水面・線路・公園」でも緩和されない
よくある誤解として、「北側が公園や川(水面)、線路に面していれば緩和される」というものがあります。
道路斜線制限や隣地斜線制限の場合:では、敷地が公園、広場、川(水面)、線路敷地などに接している場合、その公園や川自体の幅の1/2だけ、境界線が外側にあるものとみなす緩和措置があります。
しかし、「北側斜線制限」に関しては、この緩和措置は適用されません。
北側にある公園や広場も、将来にわたって日照を確保すべき場所とみなされるためです。土地選びの際、「北側が公園だから日当たりが良いし、制限も緩和されるだろう」と誤解しないよう、十分にご注意ください。
-
土地購入前に確認すべきチェックリスト
-
-
用途地域と斜線制限の有無を調べる
まずは、建物を建てたい場所がどの用途地域に当てはまるのか事前にインターネットや都市計画課等の窓口で確認しておきましょう。もし、北側斜線制限がかかるのであれば、具体的にどのような制限がかかるか把握しておきましょう。
土地価格が安いときは「制限が厳しい可能性」を疑う
あまりにも土地の価格が安いと疑問に思ったら、その土地にかかる制限は厳しいのではないかと疑ってみることも大切です。北側斜線制限が厳しかったり、他の法令上の制限が厳しかったりして理想のお家を建てられない可能性も十分にあります。周辺の相場を調べてみたり、不動産会社に相談してみることをお勧めします。
想定している建物が建てられるか事前に設計士に相談
北側斜線制限が適用される場合、設計の自由度が制限されます。そのため、希望する間取りや建物の高さや屋根の形が実現可能であるか、土地を購入する前に設計士に相談しておくと安心です。
あわせて読みたい

こんな土地には注意して!土地探しで気を付けたい3つのポイント
-
まとめ
-
-
今回は、北側斜線制限におけるルールや緩和措置について説明いたしました。
土地は用途地域で分けられており、その地域ごとに建物の高さや形状の制限が課されます。
つまり、言い換えればこの制限があるからこそ、ご自身の日照や通風、景観が保たれています。制限は、一定の要件を満たせば緩和できるケースもあります。お互いに、快適で居心地の良いお家を建てるためにも、ルールを守ったうえでお家づくりを検討しましょう。
弊社には、「HOLIDAYS」という注文住宅部門もございますので、お土地探しから理想のお家づくりまで、ワンストップで提案が可能です。是非お気軽にご相談くださいませ。


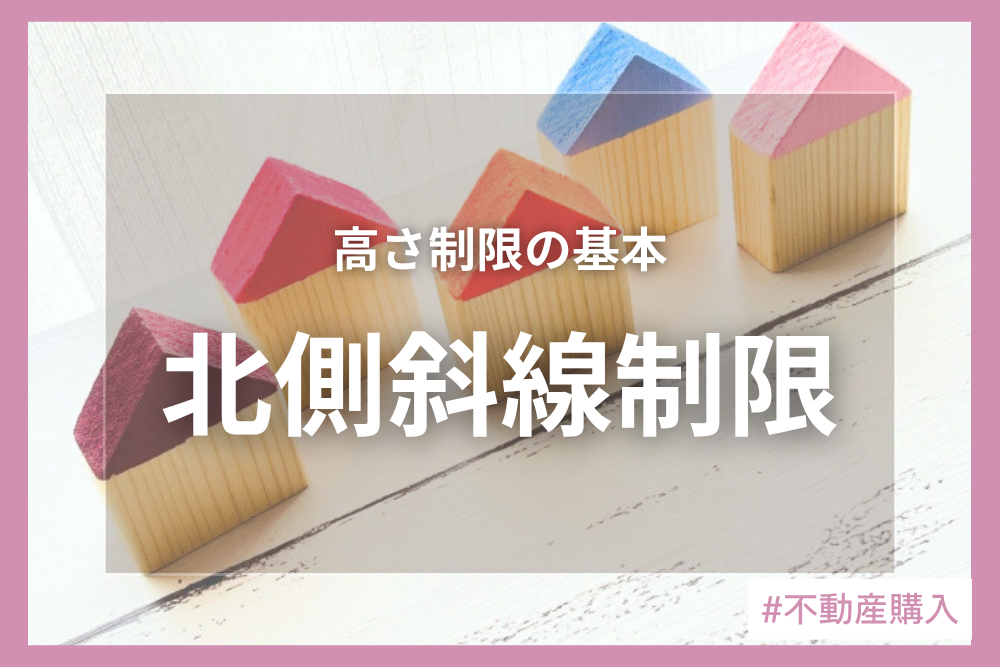





 物件を実際に探してみよう!
物件を実際に探してみよう!