あわせて読みたい


投稿日:2024年11月13日
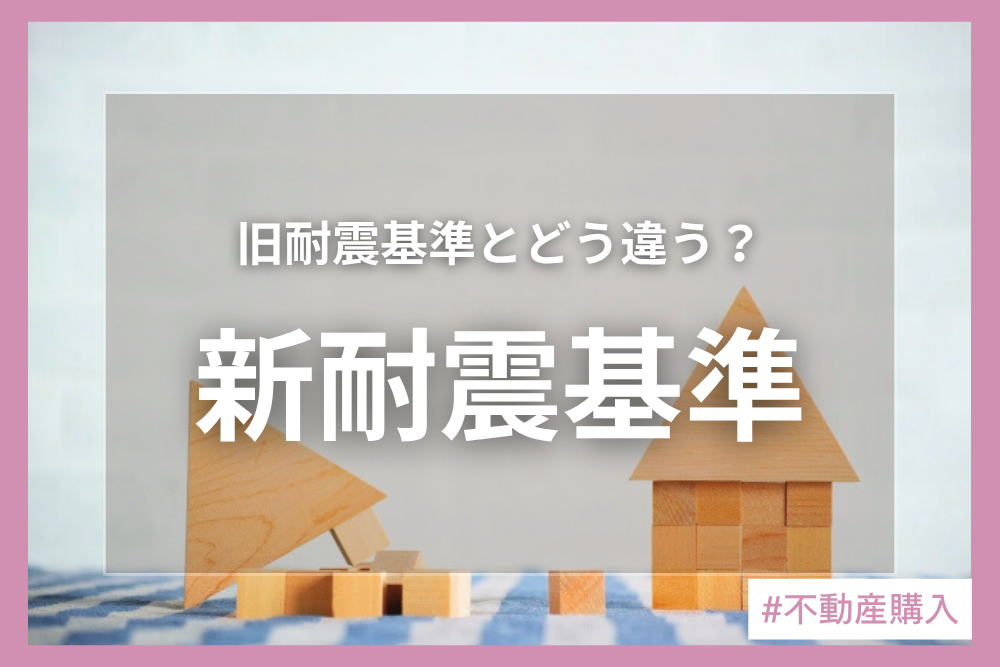
物件探しをする際に、「新耐震」や「旧耐震」という言葉を聞いたことがある人が多いと思います。
これらはある程度の地震にも耐えられるよう、建築基準法や施工法に定められた最低限の基準です。
今回のコラムでは、新耐震基準と旧耐震基準の違いや耐震性を高める住まいづくりのコツについてお話しますので、是非最後までご覧ください。
地震に耐えうる構造の基準として1981年5月31日までの建築確認に適用されていた基準です。この基準では、中規模の地震(震度5強程度)の揺れであれば建物が倒壊せず、破損した場合でも補修を行えば居住可能であることを前提としていました。
ただし、旧耐震基準は中規模地震での耐震性を目標としていたため、震度6以上の大規模地震に対する耐久性の基準はなく、近年の大規模地震に対しては、十分な安全性を備えていないとされています。
旧耐震基準が改正され、1981年6月1日以降の建築確認に適用されている基準です。この基準では、震度6強から7程度の大規模地震でも建物が倒壊や崩壊しないことを目標としています。中規模の地震では、軽微なひび割れ程度にとどめ、建物の安全性を確保することが求められています。
旧耐震基準では「許容応力度計算」による検証のみが行われていましたが、新耐震基準では、まず「許容応力度計算」によって日常的な安全性を確認する一次設計を行い、次に「保有水平耐力計算」によって、大規模地震に耐えられる水平耐力が備わっているかを確認する二次設計が加えられました。
許容応力度計算
まず人や家具、建物自体の重さ等の建物にかかる荷重を算出し、それぞれの部材にかかる応力を計算します。その後、各部材の強度と比較し、耐久性が保たれているかを確認します。
保有水平耐力計算
まず建物全体が受ける水平方向の力を合計し、倒壊しない強さを持っているかをチェックします。その後、部材が地震で変形しても壊れないよう、靭性を評価します。さらに、各階ごとに地震力が均等に分散されるよう計算し、建物全体の耐力が設計目標に達しているかを確認します。
阪神淡路大震災
1995年に発生した最大震度7の阪神淡路大震災では、約104,906棟が全壊し、144,272棟が半壊。このうち、被災した98%の木造住宅が旧耐震基準で作られた家であったことが日本建築学会の「阪神・淡路大震災調査報告書」で分かっています。
熊本地震
2016年に発生した最大震度7の熊本地震では、約86000棟が全壊、34000棟が半壊。このうち、旧耐震基準の倒壊率は28.2%で、新耐震基準の倒壊率は8.7%でした。やはり新耐震基準の建物と比べ、地震に対する耐久性が大きく劣ることが分かった一方で、新耐震基準の建物の倒壊率が低かったことは、基準の強化が建物の安全性に大きく貢献していることを裏付けました。
阪神・淡路大震災の教訓を受け、新耐震基準がさらに改正され、耐震性能の強化が図られたものが2000年基準となります。この改正では、従来の耐力壁の強化に加え、構造全体のバランスを考慮した四分割法が導入され、地震に対する安定性が向上しました。

・建築確認通知書を確認する
建築確認通知書に記載されている「建築確認日」を確認しましょう。建築確認通知書は、着工前に各種法令に沿っているかを審査する建築確認申請が受理された際に返却される書類で、一般的には引渡し時に購入者に渡されます。
・耐震基準適合証明書を確認する
耐震基準適合証明書とは、住宅などの建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。この証明書は、耐震基準確認のためだけでなく、住宅ローンの借入時や住宅ローン控除を受ける際に必要となります。この証明を発行するためには、耐震診断が必要となります。
・建築に関する調査書を取り寄せる
建築確認証明書を紛失している場合は、敷地面積や建物の大きさ・高さ、配置図などが記載されいている「建築計画概算書」、建築確認や検査が行われた建築物であるかについて記載されている確認済証や検査済証を紛失した場合に発行する「建築確認台帳記載事項証明書」などの建築に関する調査書を取り寄せることで確認が可能です。

住宅の耐震性を考える際、建物の構造だけでなく、その土地の地盤も重要なポイントです。例えば、固い岩盤や砂礫層の土地は、地震の揺れが伝わりにくく、大雨や地震、津波といった災害にも強い特徴があります。このため、土地購入時には過去の航空写真やハザードマップを活用し、自然の地形に近いかどうかや盛り土の有無をチェックして、地盤の種類や特性をよく確認すると良いでしょう。
建物の柱や梁など主要な構造部材の強度を高めたり、耐力壁をバランスよく配置することで、地震の揺れに耐える力を分散させることができます。また、接合部に金物を使用し、柱や梁が外れにくい構造にすることで、さらに安全性が向上します。構造体部分から強化することで、家全体が地震の揺れを吸収しやすくなり、倒壊のリスクを低くすることができます。
建物が重いほど地震の揺れを受けた際の力も大きくなるため、建物の軽量化を意識するとよいでしょう。特に屋根を軽量化することで、建物全体の重心を低く保つことができ、地震時の揺れを抑える効果もあります。
2階にリビングを配置することで、1階に寝室や子ども部屋などの個室を設けやすくなるため、1階の柱や壁の数が増え、建物全体の耐震性が向上します。また、地震で建物が倒壊した場合、2階にリビングがあることで下敷きになりにくく、家族の安全性も高まります。
現在お住まいの家や住み替え先の家の耐震性に不安がある場合は、補強工事することをおすすめします。費用は大まかな目安として数十万円から数百万円程度かかることが多いですが、具体的な費用は工事内容や建物の状態により異なります。
また、名古屋市では、1981年5月31日以前に着工した木造住宅を対象に「木造住宅無料耐震診断」を行っています。この診断により、耐震性の評価を受けることができ、必要に応じて補強工事の計画を立てやすくなります。
一定の耐震改修工事を行った際、その費用の10%が所得税額から控除される制度です。こちらは「投資型減税」としての側面があり、主に耐震改修に対する投資を促進するための税制措置となっています。
[条件]
(既存住宅の条件)
①申請者の居住の用に供する住宅であること
②昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基 準に適合していないものであること
(耐震改修の要件)
③現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること


今回は新耐震基準と旧耐震基準の違いや、耐震性を高めるための住まいづくりのコツについてお話ししましたがいかがでしたでしょうか。
特に中古戸建の購入をご検討されている方は、検討中の物件が「新耐震基準」か「旧耐震基準」かをまず確認することが必要です。ただし、旧耐震基準の物件であっても耐震補強工事をすることで耐震性能を向上させることができますのでご安心ください。
ハウスボカンでは物件のご紹介だけでなく、不動産のプロの目線で物件探しのコツも併せてお伝えさせていただきます。物件購入をご検討中の方はまずは一度店舗にご来店いただき、お気軽にご相談くださいませ。
 物件を実際に探してみよう!
物件を実際に探してみよう!不動産購入の知識がついたら物件を探してみよう!会員登録すれば物件検索の幅がグッと広がります!

メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ